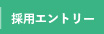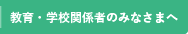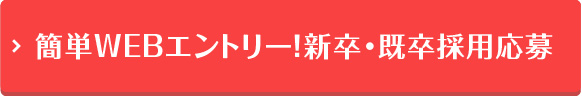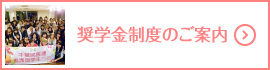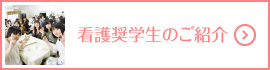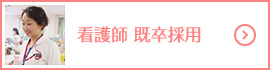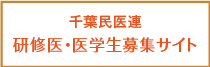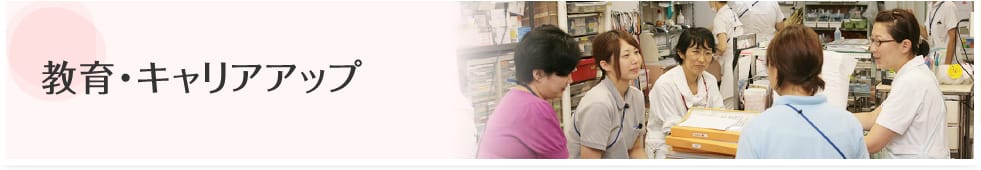









































9月の奨学生ミーティング&国家試験対策講座は
奨学生ミーティング「コロナ禍、地域では何が起きている!?~地域包括支援センターの役割を知る~」
8月に開催した医系サマーフェスではコロナウィルスについての概要が焦点でした。
9月の看護奨学生ミーティングはそれを受け、コロナは地域医療・介護の中でどんな影響を及ぼしているのか?を学ぶことになりました。
今回もリモートミーティングで開催。講師は二和・八木が谷地域包括支援センターの社会福祉士、Kさんです。
まず、地域包括支援センターの構成員、主な業務についてお話いただきました。
地域包括支援センターは保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種がチームとなって、それぞれの専門性を生かしながら、適切な機関へ繋ぐ役割を担います。
高齢者の皆さんやその家族からの介護や福祉、医療、健康、認知症のことなど様々な相談に応じ、いつまでも健やかに住み慣れた地域で暮らせるように支援を行う相談窓口です。
地域包括支援センターの主な業務は
①総合相談支援業務
「デイサービスに行って運動したい」、「自宅の玄関に手すりをつけたい」、「入院先から介護保険の申請をするように言われたけど、どうしたらいい?」等々、様々な相談があります。
②介護予防ケアマネジメント業務
要支援1・2の認定を受けた方、事業対象者がサービスを利用できるようにお手伝いします。介護予防教室の開催など。
③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
地域のケアマネージャー支援(ご担当されているケースの相談等)
地域の支援者とのネットワークづくり(地域ケア会議、支援者の交流会の開催等)
④権利擁護業務
高齢者虐待やその疑いが通報された時に対応(高齢者虐待の防止・早期発見)。
認知症等により、適切な判断が難しくなった方が、そのことで不利益が生じないように支援する(成年後見制度等)。
消費者被害等の啓発等。
様々な業務があるということを知りました。
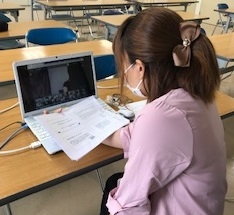
今回は低学年の看護奨学生が27名参加しました。4グループにわかれて自己紹介や近況報告も入れながら、ディスカッションしました。
事例①「新型コロナウィルス感染症の流行により発生した虐待」(自粛期間にずっと家族一緒。口論からエスカレートしたケース)では、ディスカッションの後、地域包括支援センターの保健師が担った役割についてお話してもらいました。
事例②「新型コロナウィルス流行により、受診控え、サービス未利用。病状の増悪」では、病院の感染対策など専門職ならではの情報や知識を使い、受診につながるように支援することが必要だとわかったという感想がありました。
家族虐待のケースについては、大半の人が誰が悪いのではなく『環境がそうさせている』という意見でした。そしてこれが特別なケースではなく、コロナ禍ではどこでも起こり得ることなのだと考えた学生が多かったです。
自粛期間のストレス…。私たちも思い当たります。
そうなってしまう前に周囲の第三者が手を差し伸べていたら。SOSを出せない人のサインをいかにキャッチできるか、医療機関より身近に地域包括支援センターがあることの意義は大きいです。
そして、不幸にも虐待が起こってしまったら、「虐待してしまった人のケアも大事」。Kさんの言葉が印象的でした。
(写真はディスカッションしている学生です)

看護師国家試験対策講座「在宅看護Ⅱ」
7月「解剖生理」、8月上旬「必修問題」、8月下旬「在宅介護Ⅰ」に続いて今回は4回目。
講師に訪問看護ステーション所長を招き、今回もリモートで行いました。
参加した学生からは「一つの問題から、その周辺の知識まで教えてくれて、ためになりました。」、「在宅は保健師過程の中で重要でもあるため、保健師国家試験対策にもつながり、有意義でした。」等の感想がありました。
全8回シリーズの看護師国家試験対策講座。受験生もいよいよ本腰を入れる時期になりました。

その他の記事を見る
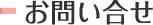
東京駅から職場まで60分、都心にも近い職場です。 アクセスはこちら
Copyright (C) CHIBA MIN-IREN All rights reserved.